for peopleからのお知らせ Information
覚えておきたいアパレル用語まとめ!アパレル・ファッション関連の専門用語
- NEWS
2025.04.30
覚えておきたいアパレル用語まとめ!アパレル・ファッション関連の専門用語
- NEWS
2025.04.30

アパレル業界には多様な専門用語が存在し、転職や就職を考えている方、業界経験の浅い方にとっては「聞いたことはあるけれど意味がよくわからない」と悩むことも多いのではないでしょうか。
店舗で使用される用語だけでも「旗艦店」「SKU」「社販」など独特な言葉が多く、さらにブランドに関するカテゴリやEC、ビジネス関連の用語、SNSマーケティングに至るまで幅広い知識が求められます。
こうした言葉の意味を理解しておかないと、日々の業務や商談、面接時のコミュニケーションで困ってしまう可能性があります。
そこで本記事では、「店舗で使用する用語」「ブランドに関する用語」「ECに関連する用語」「アパレルビジネス関連の用語」「アパレルに関連するSNSマーケティング用語」という5つのカテゴリに分けて、それぞれのキーワードを分かりやすく整理しました。
用語の意味だけでなく、現場でどう活用されているのかも簡潔に解説するので、業界初心者からさらなるスキルアップを目指す方まで幅広く役立てていただける内容になっておりますので、ぜひ参考にしてください。
店舗で使用する用語

店舗オペレーションや販売の現場では、独特の言い回しや略語が多く使われています。
ここでは、初心者の方にもわかりやすいよう、それぞれの用語についてポイントを押さえつつ解説します。
実際の業務でどのように使われ、どんなメリットや注意点があるのかを学ぶことで、店舗運営や接客の質を一段と高めることができます。
旗艦店(きかんてん)
ブランドのイメージを代表するメイン店舗のことを指します。通常は大都市の繁華街や主要な商業施設に出店し、最新のディスプレイやサービスを導入するなど、ブランド力を強くアピールする場として重要視されます。面接などで「旗艦店配属」と聞いた場合は、ブランドの顔として働く可能性が高いため、接客技術や商品知識の深さがより求められます。
直営ショップ(直営店)
ブランドやメーカー自身が直接運営する店舗で、商品の発注や売り上げ管理も一括して行います。ブランド戦略を反映しやすく、正確な商品情報やアフターサービスを受けられるのが特徴です。転職先が「直営店」か「フランチャイズ」かによって業務内容や待遇が変わるケースもあるため、応募時にチェックしておくとよいでしょう。
館(やかた)
百貨店やショッピングモールなど、複数の店舗が入っている大型商業施設を指すことがあります。テナントとして出店しているブランドは、この“館”ごとの集客力や特徴を踏まえた販売戦略が必要です。館の顧客層やイベントスケジュールに合わせてディスプレイを変更したり、他テナントとのコラボ施策を行うこともあります。
オフプライスストア
セール品やシーズンオフの商品を割引価格で提供する店舗のことです。定価(プロパー価格)よりも安い価格帯で販売されるため、在庫処分や集客アップの役割を果たします。商品を安く手に入れたい顧客にとって魅力的な反面、売り場の混雑やサイズ欠けなどの課題も生じやすい点を理解し、スタッフは細やかな接客対応が求められます。
ボディ・トルソー
服を陳列・展示するための人体形のマネキンです。全身タイプを「マネキン」、上半身だけを展示する場合を「トルソー」と呼ぶことが多く、商品のシルエットやコーディネートを視覚的にわかりやすく見せる役割があります。顧客に「着用イメージ」を具体的に伝えられるため、売れ筋商品のコーデ例を積極的に打ち出すと購買意欲を高めやすいです。
パッキン
商品の梱包に使用する段ボールやビニール袋などの総称です。流通過程での汚れや破損を防ぐ役割を持ち、店舗・倉庫・物流センターなど各所で使用されています。取り扱いに不備があると商品トラブルにつながり、顧客満足度の低下を招くため、丁寧かつ正確な梱包作業が不可欠です。
ディスプレイ
店頭や店内で、ブランドの世界観や季節感を表現するための陳列方法を指します。視線誘導を意識した配置や色の組み合わせで商品の魅力を最大限引き出すことが重要です。新作や目玉商品をどこに、どのように配置するかによって売り上げが大きく左右されるため、定期的な見直しやディスプレイ替えを行いましょう。
プロパー価格
割引やセールを行う前の定価のことです。店舗ではプロパー価格の商品が売り場の主力となり、シーズン終盤や在庫調整時にセールへ移行することが一般的です。顧客に対して「セール前に買う価値」があることを上手に伝えることで、早期完売を目指す戦略を立てることができます。
SKU
「Stock Keeping Unit」の略称で、在庫を管理する最小単位を指します。色やサイズごとに商品を区分するため、小売業やアパレル店舗の在庫管理には欠かせない概念です。SKUをしっかり管理しておくと、欠品や過剰在庫を防ぎ、店舗の売り上げを安定させることにつながります。
社販
社員販売の略称で、ブランドスタッフが社内価格(社員割引)で商品を購入できる制度を指します。スタッフが実際に着用することでブランドの理解や愛着が深まり、接客にも好影響を与えることが多いです。多くのアパレル企業が導入しており、応募者にとっては福利厚生としての魅力にもなります。
プレセール
本格的なセールが始まる前に、一部顧客や特定の会員向けに先行して行うセール施策です。会員ランクの高い顧客やリピーターを優遇することで、顧客満足度を高めると同時に在庫調整もしやすいメリットがあります。スタッフは「限定感」を丁寧に伝えることで、リピーター化を促進できます。
B品 (DD)
傷や汚れなどの理由で正規品として販売が難しくなった商品を指します。外観にわずかな難があっても着用には問題がないケースも多く、B品専門のセールやアウトレットで販売されることがあります。店舗側はB品の取り扱いと在庫管理を徹底し、通常商品との混在を防ぐことでトラブルを回避します。
死に筋
売り上げが極端に低迷している商品や、在庫が動いていないアイテムのことです。長期間売れ残ってしまうと、保管スペースの圧迫や資金回収の遅延など経営にダメージを与えます。早期に値下げや販促を行い、テコ入れを図ることが重要です。
検品(けんぴん)
商品が入荷した際、縫製不良や汚れなどがないかをチェックする作業です。アパレル店舗では品質の安定や返品・交換リスクの最小化を目的として欠かせない工程となります。特にハイブランドやフォーマルウェアなどは厳格な検品基準を設けていることが多く、スタッフの注意力も問われます。
キャッシャー
レジ業務を行うスペースや、そこに立つスタッフを指すことがあります。現金やクレジットカードの取り扱い、会計ミス防止など高い正確性が求められるポジションです。キャッシャー担当は接客の締めくくりを担うため、笑顔での対応や追加商品を提案するなど、店舗の売り上げ拡大にも貢献できます。
キャリー品
前シーズンから継続して販売される商品を指します。定番商品やロングセラーアイテムが該当することが多く、安定的な売り上げを見込める一方、新作との陳列バランスも大切です。シーズンをまたいで販売できるため、接客時には「長く愛用できる」といったメリットを伝えると効果的です。
ハンギング
服をハンガーに掛ける陳列方法のことです。「平置き」と比較して商品全体のシルエットを見せられるため、デザインやサイズ感を直感的に理解してもらいやすい特徴があります。ただし、スペースを取るため限られた面積を効率的に使う工夫が必要です。
フェイス
商品を正面向きに並べる陳列手法を指します。視覚的に商品の特徴を捉えやすいため、新作や目玉商品などをフェイス陳列すると効果的です。ただし、あまりにフェイス商品ばかり増やすと売り場が煩雑になる恐れがあるため、バランスを意識しましょう。
バックヤード
商品や備品の保管場所、店員の休憩スペースなどを兼ねた店舗の裏側エリアです。限られたスペースを有効活用し、効率的に在庫を出し入れするための整理整頓が欠かせません。バックヤードの整備状況は作業効率だけでなく、スタッフの士気にも影響します。
在庫管理
入荷から販売まで商品の数量や状況を把握し、欠品や過剰在庫を防ぐために調整する業務です。売れ筋や死に筋を分析することで、適切な発注量と売り場づくりにつなげることができます。POSシステムや在庫管理ソフトを導入する店舗も多く、正確なデータを用いた戦略立案が求められます。
商品管理
在庫管理を含め、商品の状態や品質、陳列状況などを総合的に管理するプロセスです。シワや汚れがついていないか、サイズ展開に抜けがないかなど、細部にわたってチェックし、顧客がいつでも最適な状態で商品を手に取れるように維持することが重要となります。
パッキン
上記で紹介した段ボールや包材など梱包物のことを、店舗によっては繰り返し呼称する場合があります。入荷時の作業効率や返品対応などで用いられる言葉ですが、重複して混在しないようスタッフ間の用語統一を図ると良いでしょう。
上代(じょうだい)
小売価格を意味し、一般的には販売価格として認識されています。適正な上代設定ができているかどうかは、売り上げやブランドイメージにも大きく影響します。高すぎると売れ残り、低すぎると利益が薄くなるため、マーケット調査や競合分析が欠かせません。
下代(げだい)
卸売価格や仕入れ価格を指し、小売業者が商品をブランドやメーカーから購入する際の金額をいいます。上代と下代のバランスが利益率を左右し、店舗ビジネスの存続にも直結します。交渉力のあるバイヤーほど下代を有利に設定できるケースがあります。
顧客
商品を購入するお客様を指します。アパレル店舗ではリピーター育成が売り上げ向上のカギとなるため、一度きりで終わらないように顧客データを蓄積し、好みや購入履歴を把握してCRMを行います。顧客のニーズを正確に捉えるほど、接客満足度が上がり、リピート購入につながります。
客注
店頭にない商品を顧客からの注文を受けて取り寄せることです。他店や倉庫の在庫を活用することで顧客満足度を高められますが、取り寄せまでに時間がかかる場合もあるため、入荷予定や配送状況を随時確認して顧客に連絡することが重要です。
客単価(きゃくたんか)
1人の顧客が購入する金額の平均値を示します。客単価を上げるにはセット販売やクロスセルが有効ですが、押し売りにならないよう「顧客のライフスタイルや好み」に合わせた提案が求められます。スタッフが商品知識やコーディネートスキルを持つことで、自然なアップセルが実現しやすくなります。
セット率
複数アイテムを同時に購入してもらう割合を指します。トップスとボトムス、バッグやアクセサリーなどトータルコーディネートを提案することで、売り上げ増加だけでなく、顧客満足度の向上にもつながります。見本コーデや着回し術の紹介など、付加価値のある提案力が鍵です。
ショッパー
商品を持ち帰る際に使用する紙袋やビニール袋のことです。ブランドロゴが大きくあしらわれている場合が多く、顧客が街中を歩く際に広告塔になるメリットも期待できます。環境問題への意識が高まる昨今は、再利用しやすい素材やデザインに注目が集まっています。
薄紙(うすし)
服を丁寧に包装する際に使用する薄手の紙を指します。商品の保護だけでなく、ブランドイメージの演出にも役立ちます。ギフト需要の高い時期などは、薄紙の色や柄をシーズンに合わせて変える店舗もあります。
CS(シーエス)
「Customer Satisfaction(顧客満足)」や「Customer Service(顧客サービス)」の略称として使われることが多いです。顧客満足度を高めるためには、スタッフ全員が商品知識とホスピタリティを兼ね備える必要があります。売り上げだけでなく、ブランドロイヤルティの向上にも直結する重要な概念です。
DM(ディーエム)
ダイレクトメールの略で、顧客に向けてキャンペーン情報や新商品の告知などを郵送やメールで行う手法です。定期的に行うことで来店を促進し、他店との情報競合を勝ち抜くためにも有効です。個人情報の保護や配信頻度などにも配慮し、顧客に煩わしさを与えないよう適切な運用が求められます。
1番.2番.3番
販売や陳列での優先順位や、スタッフ間の役割分担を数字で示すことがあります。例えば「1番はレジ担当、2番はフィッティングサポート」など、現場でのオペレーションをスムーズに進めるための合図として用いられます。スタッフ同士の意思疎通が円滑になるメリットがある一方、慣れていない人には分かりづらい場合もあるため、明確なルール設定が大切です。
MD
「Merchandiser(マーチャンダイザー)」あるいは「Merchandising(マーチャンダイジング)」の略です。適切な商品計画や在庫管理を担い、売り場づくりの戦略を立案します。MDが店舗や市場のデータを分析し、商品投入のタイミングや価格設定を行うことで、ブランド全体の売り上げを最適化します。
バイヤー
店舗やブランドで販売する商品を買い付ける担当者を指します。市場の動向やブランドのコンセプトを考慮しながら、国内外から商品を選定・仕入れする役割を果たします。仕入れコストや販売予測を同時に考慮する必要があるため、ロジカル思考とファッションセンスの両方が求められます。
ブランドに関する用語

ブランドカテゴリーやオリジンによって異なる呼称があり、価格帯やターゲット層、デザイン性などに大きく関わります。転職や就職活動時に「どのブランドを選ぶのか」を考える上でも、これらの用語はしっかり理解しておきましょう。
ハイブランド
高級ファッションブランドを指します。グローバルに展開し、歴史や知名度、デザイナーのステータスが高いブランドが該当します。顧客層は富裕層が中心で、商品価格も高めに設定されるため、接客時にはきめ細やかなサービスと商品知識が特に重要です。
ミドルブランド
ハイブランドよりも価格帯が抑えめで、比較的幅広い層が手に取りやすいブランドです。機能性やトレンドをバランスよく取り入れ、コストパフォーマンスに優れたアイテムを展開するケースが多いです。普段着から通勤着まで多彩なシーンに対応する商品ラインナップが特徴です。
セカンドライン
ハイブランドが展開する、より若年層やカジュアル層向けの手頃な価格帯のブランドラインを指します。本家ブランドのイメージを継承しつつ、デザインを大衆向けにアレンジすることで市場拡大を目指します。就職や転職時には「本ライン」なのか「セカンドライン」なのかで業務内容や客層も異なることがあります。
インポートブランド
海外から輸入されたブランドの総称です。国内ブランドでは味わえない独特のデザインやカルチャーを取り入れているため、海外ファッション好きの顧客を中心に支持を集めることが多いです。言語や通貨の違いなど、仕入れ面でも特殊なノウハウが必要となります。
DCブランド
「Designer & Characterブランド」の略称で、日本国内のデザイナーが手がけるブランドを指すことが多いです。独自のコンセプトや世界観が強く打ち出され、コレクション発表などを通じてファッションシーンに影響を与えます。価格帯はやや高めになる傾向がありますが、熱心なファンが付くことも多いです。
デザイナーズブランド
有名デザイナーや個性的なクリエイターが中心となって立ち上げたブランドです。オリジナリティが高く、斬新なデザインや前衛的なスタイルが特徴です。トレンドを生み出す源泉にもなり得るため、ファッション関連のメディアやSNSでは大きく取り上げられることが多いです。
ドメスティックブランド
国内(日本)発祥のブランドを指します。日本人の体型や嗜好に合わせたデザインを展開することが多く、品質や縫製の丁寧さが強みとなる場合があります。海外進出を目指すドメスティックブランドも増えており、グローバル展開への意欲が高い企業が多いです。
ライセンスブランド
他社や別のデザイナーからブランド名やロゴの使用権を取得して展開されるブランドです。自社オリジナル商品としてリリースする場合でも、デザインやコンセプトに制限があるため、商品づくりやマーケティングには一定のルールを守る必要があります。ライセンス料や契約期間など、ビジネス上の契約管理も重要です。
ファクトリーブランド
生産工場が直接手がけるブランドで、中間マージンを省くことで高品質ながらリーズナブルな価格を実現するケースが多いです。製造背景が明確であることも信頼感につながり、サステナブルな姿勢を重視する顧客からの支持を得ることが増えています。
ECに関連する用語

オンラインでの販売チャネルが拡大する中、EC関連の用語を理解しておくことはアパレル業界でのキャリアを考える上でも重要です。商品の売り上げを伸ばすだけでなく、顧客との継続的な関係構築にも直結するポイントが多いので、基本的な概念をしっかり把握しましょう。
EC
「Electronic Commerce(電子商取引)」の略称で、インターネットを通じて商品を売買する仕組み全般を指します。自社サイトやオンラインモールなど、多様な形態があり、昨今ではスマートフォンのアプリによる販売も盛んです。実店舗と合わせて展開することで売り上げとブランド認知を高める戦略が一般的になっています。
越境EC
国境を越えて行われるECのことです。国内だけでなく海外顧客をターゲットに商品を販売することで、売り上げの拡大を図ります。言語対応や関税、輸送コストなどクリアすべき課題はありますが、グローバルなブランド認知の向上にもつながるため、多くのアパレル企業が注目しています。
チャネル
商品やサービスを顧客に届けるための経路を指し、店舗やECサイト、SNSなどがチャネルの例です。チャネルを増やすことで顧客との接点を増やせますが、すべてのチャネルを適切に運営しきれないとコストや管理が肥大化します。自社のターゲットやブランド特性を踏まえたチャネル戦略が不可欠です。
オムニチャネル
実店舗とECを含めた多様なチャネルを連携させ、一貫した顧客体験を提供する戦略を指します。オンラインで購入した商品を店舗で受け取る「クリック&コレクト」などが代表例です。顧客データの一元化や在庫連携が必要で、ITシステムの整備やスタッフ教育にコストがかかりますが、利便性と満足度が向上するためリピーターが増えるメリットがあります。
オンラインモール
複数のショップやブランドが集まるECサイトの総称です。大手プラットフォームの集客力を利用し、多くの顧客にアプローチできる反面、手数料や競合ブランドとの比較・競争が激しいという特徴があります。出店を検討する際には、モールの利用層と自社ブランドのターゲットが一致しているかを確認しましょう。
ライブコマース
ライブ配信を通じて商品を紹介・販売する手法です。リアルタイムで視聴者の疑問に答えながら商品の魅力を伝えられるため、購入意欲を高めやすい点が特徴です。インフルエンサーやブランドスタッフが出演するなど、演出次第で大きな売り上げにつながる可能性があります。
OtoO
「Online to Offline」の略称で、オンライン上の施策をきっかけに実店舗での購入や来店へつなげるアプローチを指します。たとえばWEBクーポンを発行し、店舗で提示すると割引が受けられるなど、オンラインとオフラインを連動させた購買体験が目的です。 最近では逆の「Offline to Online(オフラインからオンラインへ誘導)」も重視されるようになっています。
アパレルビジネス関連の用語

実際の販売現場だけではなく、アパレル業界全体のビジネスモデルや戦略を理解しておくと、キャリアアップや転職時のアピールにも役立ちます。ここでは特に重要なキーワードをまとめました。
D2C
「Direct to Consumer」の略称で、メーカーやブランドが小売店などを通さず、直接消費者に商品を販売するビジネスモデルです。SNSやECを活用したデジタルマーケティングが中心で、消費者とのダイレクトなコミュニケーションが特徴です。小規模でも始めやすく、商品開発から販売まで一貫してコントロールできるメリットがあります。
ファストファッション
低価格かつ短いサイクルで商品を展開するファッション業態を指します。旬のトレンドを素早く取り入れ、シーズンごとに大量生産・大量販売することで常に新鮮なラインナップを提供します。環境負荷や大量消費への批判も高まっており、近年はサステナブルなアプローチに切り替える動きも見られます。
QC
「Quality Control(品質管理)」の略称です。生地や縫製、仕上がりなどが基準を満たしているかを確認する工程を指します。アパレルでは製造過程や入荷後の検品など多段階でQCを行うのが一般的で、ブランドイメージ維持の要となります。
CRM
「Customer Relationship Management(顧客関係管理)」の略称で、顧客データを分析し、リピーター獲得や顧客満足度向上を目指す手法です。ポイントカードや会員登録、メールマガジンなどを活用し、顧客一人ひとりの好みを把握してパーソナライズされた接客・販促を行います。
展示会
新作商品やコレクションの発表を目的に開催されるイベントです。バイヤーやメディア関係者向けに行われるケースが多く、商品の受注やブランドの認知度拡大を狙います。国内外のファッションウィークやショールームなどで展示会を行い、次シーズンのトレンドを世に発信する場となることもあります。
アパレルに関連するSNSマーケティング用語

現代のファッション業界において、SNSは商品情報の拡散やブランディングに欠かせない存在です。
ここでは、アパレルに関するSNSのマーケティング用語を解説していきます。
インフルエンサーマーケティング
SNSで影響力を持つ個人(インフルエンサー)を起用して、商品の宣伝やブランドイメージ向上を図るマーケティング手法です。フォロワー数だけでなく、ファッションジャンルとの親和性やエンゲージメント率が高いインフルエンサーを選定することが成功のポイントです。費用対効果の測定が難しい場合もあるため、クーポンコードやトラッキングリンクを活用して効果検証を行います。
UGC
「User Generated Content」の略称で、ユーザーがSNSやレビューサイトなどに投稿するコンテンツを指します。実際に購入した人のコーデ写真や口コミは信頼性が高く、ブランド側がUGCを積極的にシェアすることで好印象を与えられます。UGCを増やすためには、ハッシュタグキャンペーンやレビュー投稿特典などの施策を行うのが一般的です。
まとめ
アパレル業界の専門用語を把握しておくと、現場や面接で役立つだけでなく、ファッション情報をより深く理解できるようになります。店舗運営からEC、SNSまで幅広く押さえておけば、顧客への対応や売り場づくり、キャリアの選択肢も広がるはずです。
まずは本記事で紹介した用語を参考に、自身の業務や学習に活かしてみてください。より深い知識を得ることで、ファッションを通じた新たなチャンスを掴めるでしょう。
for peopleは、社員全員がアパレル業界出身のメンバーで構成されており、アパレル業界に特化した転職支援・人材紹介事業を展開しています。
アパレル店員・販売員はもちろん、様々な職種の転職先をご用意しています。
幅広い転職先と実績がございますのでぜひご覧ください!
株式会社フォーピープルの強みは
①社員全員がアパレル業界出身なので業界知識に精通している!
②経験を活かせる企業への推薦や非公開求人への応募が可能!
③未経験から本社職にキャリアアップできるスクール事業を展開している!
また、毎週火曜日夜のみ原宿でオープンするアパレル関係者限定のBar “Fashion Tuesday”事業や、
アパレル業界に特化したEC・SNSの運用支援事業なども展開しています!


Author Profile
- 株式会社フォーピープル
代表取締役
文化服装学院を卒業後、SPAレディースアパレルで営業・MD職を経験、
その後OEM企業での営業生産職を経て株式会社フォーピープルを設立。
アパレルOEMに加え、EC出店代理店事業やイベント事業を経て、
現在はアパレル業界に特化した転職支援事業を主軸とした営業会社というビジネスモデルを確立。
デジタルとアナログのクロスマーケティングを得意とし、業界内外の様々なネットワークを駆使し事業を拡大している。
Latest entries
 NEWS2025年5月1日パタンナーの仕事内容とは?必要なスキル・やりがい・年収までを徹底解説!
NEWS2025年5月1日パタンナーの仕事内容とは?必要なスキル・やりがい・年収までを徹底解説! NEWS2025年5月1日アパレル業界の事務職とは?主な仕事内容を解説
NEWS2025年5月1日アパレル業界の事務職とは?主な仕事内容を解説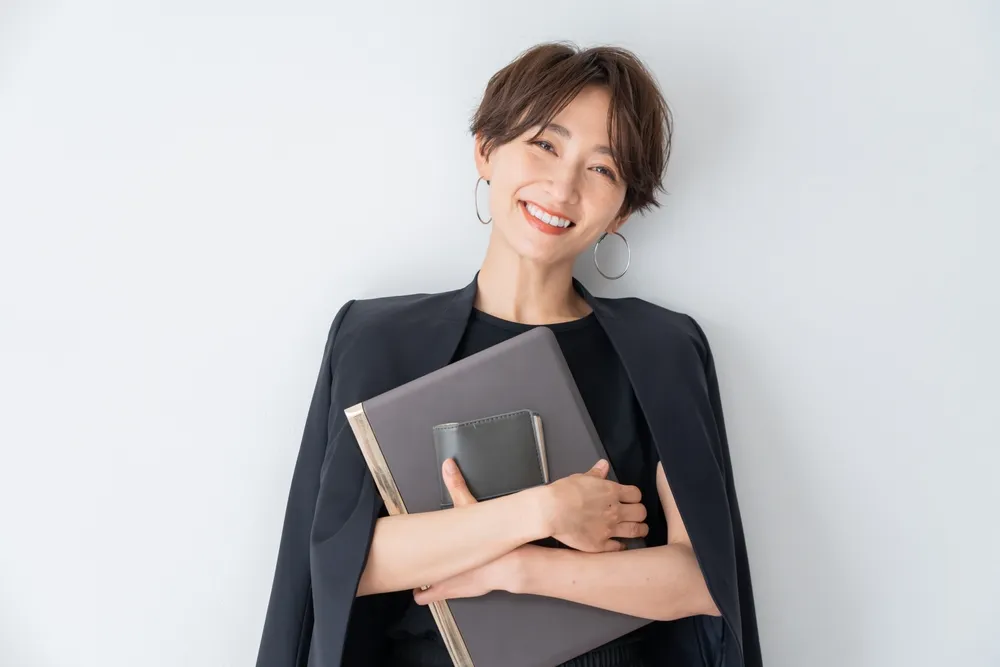 NEWS2025年4月30日アパレルのプレス・PRとは?仕事内容やどんなスキルが必要か解説
NEWS2025年4月30日アパレルのプレス・PRとは?仕事内容やどんなスキルが必要か解説 NEWS2025年4月30日アパレルの営業とは?仕事内容や向いている人の特徴を解説
NEWS2025年4月30日アパレルの営業とは?仕事内容や向いている人の特徴を解説
















